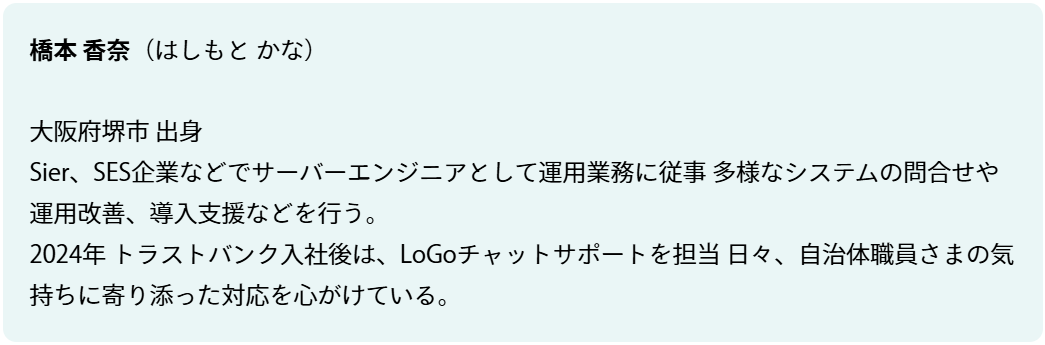前編では、LoGoシリーズのテクニカルサポート担当、橋本さんのお話から、自治体職員さん一人ひとりの心に寄り添う真摯な姿勢を明らかにしました。それは、単なる機能説明や問題解決に終わらない、人間的な温かさに満ちた考え方でした。
後編では、その考え方が生まれる土壌、すなわちトラストバンクのパブリテック事業部という組織のカルチャーについて、さらに深くお話ししていきたいと思います。
なぜ私たちは、これほどまでにプロダクトに情熱を注げるのでしょうか。その答えは、橋本さんが語ってくれた、入社後の「驚き」と、私たちの組織に根付く「特徴」の中に隠されていました。
入社して最も衝撃を受けた「プロダクト愛」
「トラストバンクに入社して、最も衝撃を受けたのは、社員の皆さん、特に開発チームの『プロダクト愛』の深さでした。」これまで複数のIT企業でキャリアを積んできた彼女の目には、トラストバンクの文化が非常に新鮮に、そして力強く映ったそうです。「前職までは『うちの子は、もうこういう子ですから…』と、どこか限界を前提に話す感覚がありました。ですが、トラストバンクでは全く違うんです」。
「うちの子は、いい子なんです」——限界を設けない開発思想
「ここでは、皆が自分のプロダクトを『我が子』のように捉えています。『うちの子は本当にいい子で、素晴らしい可能性を秘めている。今はまだできないことも、必ずできるように私たちが責任を持って鍛え上げます』と。そんな、愛情と責任感を、日々のやり取りから感じるんです!」この想いこそが、品質に妥協せず、プロダクトを常に良い状態に保とうとする、エネルギーの源になっているのかもしれません。
テンプレート思考からの脱却を目指して
その想いは、チーム内のナレッジ共有のあり方にも反映されています。「問い合わせ対応のナレッジ共有というと、『回答文案のテンプレート』を想像しがちですが、私はその考え方に非常に慎重です。大切なのは、文案を使いこなすことではなく、その回答に至るプロダクトの仕様を深く理解することだからです。」テンプレートは思考を停止させ、応用力を奪ってしまうかもしれません。彼女が目指すのは、その先にある本質的な理解です。
共有すべきは「回答」ではなく「思考プロセス」
「私たちが共有したいのは、『こういうお問い合わせには、こういう仕様だから、こういう考え方で、こういう回答になるんだ』という思考のプロセスそのものです。」それは、単に知識をコピー&ペーストするのではなく、メンバー一人ひとりの頭の中に、問題解決のための「OS」をインストールするような、人材育成の考え方と言えるでしょう。
自治体と開発を繋ぐ「翻訳者」としての役割
プロダクトを成長させるため、開発チームとの連携はとても重要です。橋本さんは、ご自身の役割を「翻訳者」だと表現します。「私たちは、『自治体さん目線』と『開発チーム目線』、その二つを結びつけるハブのような存在です。双方の意図を正確に翻訳し、認識のズレが生じないように調整することで、プロダクトの改善サイクルはよりスムーズに、より速く回っていきます」。この地道な調整役が、プロダクトの進化を縁の下で支えているのですね。

私たちの「最大の強み」であり「差別化要因」
インタビューの終盤、橋本さんはトラストバンクの、そしてパブリテック事業部の「最大の強み」について言及しました。それこそが、満足度No.1という評価につながる、1つの要因だったのかもしれません。「パブリテック事業部には、前職が自治体職員だった方が、多く在籍しているんです。私が知っているだけでも、5〜6名はいらっしゃいます。」この事実こそが、私たちのプロダクトとサービスの大きな強みになっているのです。
「当事者」だからこそわかる、痒いところに手が届く理由
「私は入社するまで、LGWANによるネットワーク分離環境など、自治体職員の方が置かれている特殊な環境を全く想像していませんでした。ですが、元職員のメンバーの方々が、更に深い実体験をもって『現場のリアル』を社内に展開してくださるんです。」それは、表面的なヒアリングでは決して辿り着けない、深いレベルでの共感と理解です。セキュリティ要件の厳しさ、独特の承認フロー、専門用語のニュアンス。行政のお仕事を実体験として肌感覚で理解している「当事者」が社内にいること。このインサイトこそが、私たちのプロダクト開発の大切な価値となっています。
「過去の自分」を救うためのプロダクト開発
元職員の方々は、かつての同僚たちのために、そして何より「あの時、これがあれば…」と願った“過去の自分自身”を救うために、プロダクト開発とサービス開発に情熱を注いでいます。だからこそ、生み出される機能やサービスには、現場の職員の方々への深いリスペクトと共感が宿るのでしょう。インタビュアーが思わず「だから顧客満足度No.1なんですね!」と漏らしたのも、自然なことでした。それは、説得力のある答えでした。
人が人にしかできない仕事に集中できる世界へ
最後に、橋本さんにLoGoシリーズが目指す未来について尋ねました。「デジタルに置き換えられない、人間的な温かさが必要な業務に職員の方々が集中できる環境を作りたい。LoGoシリーズを通して、業務の負荷を下げ、働きやすさを向上させること。行政のお仕事をチェンジさせることが私たちの願いです。」LoGoシリーズは、行政のあり方を進化させ、その先にいる住民の方々へのサービス品質を向上させるためのプラットフォームなのです。
最高のパートナーであり続けるために
「日頃よりLoGoシリーズをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。皆様の業務が少しでもスムーズに進むよう、私たちはこれからも改善とサポートに全力で取り組みます。今後も、皆様の最高のパートナーとして、便利にご活用いただければ嬉しいです。」
プロダクトへの愛情、探究心、そして組織に根付く「当事者意識」。トラストバンクのパブリテック事業部とLoGoシリーズの挑戦は、これからも全国の自治体の方々と共に続いていきます。