

2025年の秋、自治体向けのDXソリューション「LoGoシリーズ」を提供する、私たち株式会社トラストバンクバンクは、日経BP 社が発行する「日経BPガバメントテクノロジー 2025年秋号」における「自治体ITシステム満足度調査 2025-2026」の情報共有ソフト/サービス部門で1位という評価を頂きました。
このことは、プロダクトの機能性だけでなく、全国の自治体職員さんという、日本の地域社会を支える最前線の方々から、私たちの姿勢そのものに対しても信頼をお寄せいただけた結果と、大変ありがたく感じています。
その評価の裏には、どのような思想と努力があるのでしょうか。私たちはその答えを求めて、日々、最前線で自治体と向き合うテクニカルサポート担当、パブリテック事業部 プロダクトグループの橋本さんにお話を聞きました。入社からまもなく1年。彼女の言葉から見えてきたのは、単なる問題解決に留まらない、お客様に寄り添うサポートの哲学でした。
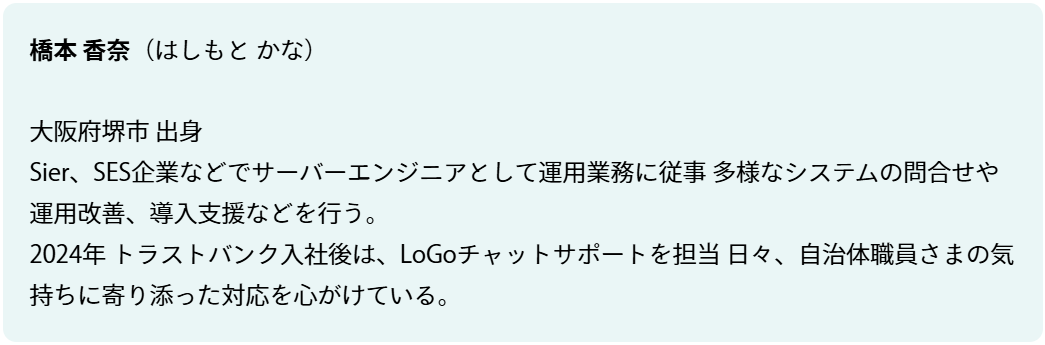
文面の奥にある「心情」を読み解く
「お問い合わせを受けた時、私が何よりも大切にしているのは、その事象や背景にある『心情』を最初に把握することです。」インタビューの冒頭、橋本さんは静かに、しかし確信に満ちた口調でそう語り始めました。自治体職員さんからのお問い合わせは、単なる事象の報告ではありません。その裏には、業務が滞る焦りや、予期せぬエラーへの戸惑いなど、様々な感情があります。彼女はまず、その気持ちを理解することから、全てのサポートを始めているのです。

事象を「立体的」に捉えるということ
「お問い合わせの文面だけでは情報が不足していることも多いため、ヒアリングをさせていただきます。その際、単に『何が起きたか』だけでなく、『なぜ起きたか』という背景、そして自治体職員さんが『今、どのような気持ちでいらっしゃるか』を想像しながら対応を進めています。」憶測で進めてしまうと、認識のズレが問題を複雑にしてしまいかねません。だからこそ、まずはお客様が置かれている状況を正しく、そして「立体的」に捉え、その気持ちに寄り添う。それは技術的な回答の前に、まず相手の心と同じ場所に立つという、信頼関係構築のための大切なステップなのです。
不安を安心に変える「最初の一言」
もちろん、いつもスムーズに対話が進むわけではありません。時には、強い不安が先行し、なかなか核心に触れる情報を得られないこともあるそうです。「そういった場合は、まずは自治体職員さんに安心してもらうことが最優先です。『大変お困りの状況ということは、私たちも理解しています。そして、その状況をできるだけ早急に解決するために、いくつか質問をさせてください』というメッセージが伝わるような言い方を心がけています。」焦りを煽るのではなく、まず安心を届ける。その一言が、対話の扉を開く鍵になることを、彼女は経験から知っています。
敬意を込めた「クッション言葉」を大切に
特に配慮しているのが、基本的な操作の確認を促す場面です。「『もうご確認済みのこととは存じますが…』といったクッション言葉は徹底しています。」当たり前の確認は、時に相手の気持ちを損ねてしまうかもしれません。だからこそ、「念には念を入れて」という姿勢で、敬意を払います。この小さな配慮の積み重ねが、自治体職員さんとの間に単なる業者と顧客以上の、パートナーとしての信頼関係を築いていく上で大切だと、橋本さんは信じています。

部署の垣根を越える、シームレスな連携体制
橋本さんのチームの強さは、個々の能力だけに支えられているわけではありません。カスタマーサクセス(CS)チームとの密接な連携もまた、その品質を支える上で不可欠な要素です。「CSの皆さんは、文字だけでは得られない貴重な情報をお持ちです。その情報共有が、本当にすごいレベルで実現されています。」
テクニカルサポートとCSのメンバーが同じチャットルームに参加し、リアルタイムで情報を共有。互いの視点からフォローし合うその体制は、自治体職員さんの課題解決という共通の目的に向かって機能しています。
未来のお問い合わせを予測するQAテスト
彼女のお仕事は、受け身の対応だけではありません。新機能のリリース前に行われるQA(Quality Assurance:品質保証)テストもまた、重要なミッションです。「新しい機能を追加する場合、私は『この機能に対して、どんなお問い合わせが来るだろうか』という観点でテストをしています」。それは、いわば未来を予測するような営みです。起こりうる問題を事前に想定し、自治体職員さんが躓きそうな点を先回りして解消しておく。このプロアクティブな姿勢が、自治体職員さんのストレスを未然に防ぎ、スムーズな体験の創出につながっているのです。
「がっかりさせたくない」という責任感
新機能への期待値は、時に想像以上に高いものです。だからこそ、「これもできると思ったのに」という落胆を生んではいけません。「自治体職員さんをがっかりさせたくないんです。だからこそ、『これができるようになります。ただし、この部分にはまだ制約があります』という情報を、先回りして、最初から明確にお伝えできるよう準備しておきます。」誠実な情報提供を行うこともまた、顧客満足度に対する大きな責任だと、彼女は考えています。
(前編ここまで)
お客様の「心情」に寄り添う共感力、不安を信頼に変えるコミュニケーション、そして未来を見据えた品質へのこだわり。前編では、橋本さんの流儀を通して、満足度No.1を支えるサポートの哲学に迫りました。ですが、なぜトラストバンクは、これほどまでにお客様の立場を深く理解し、寄り添うことができるのでしょうか。
後編では、その根源にある組織の秘密、圧倒的な強みの正体を解き明かしていきたいと思います。